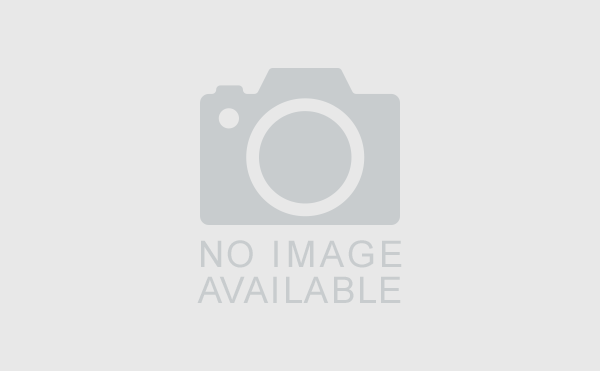離れて住む親の資産はどうするのが良いのか家族で話してみた
高齢の親に纏わる心配事
高齢の親を持つと色々な心配があります。特に私のように親と離れてすんでいて、しかも親戚が実家の近くにいない場合、仕事をしながら介護するのは困難なので、切実です。一昔前に良く耳にしたPPK(ピンピンコロリ)となれば良いですが、こればかりは努力してもどうする事ができませんね。介護は家族でできるのか?老人ホーム・介護施設にはすぐに入れるのか?施設の場所はどうするのか?遠く離れたところにある墓はどうするか?多額の借金があったらどうしよう?などなど。親の介護もお金に関わる事が多く、資産家ではない我が家のような家では、介護にかかる費用が足りるのかは気になるところです。困った時は自宅を売って何とかしよう!という家も多いのではないでしょうか。でも、親が認知症になると家は売却したり賃貸に出したりできないんです。今年の正月に兄弟が集まった時に、いい機会なので親の家や資産をどうするのか話をしてみました。
認知症になると資産はどうなる?
まずは金融資産とくに預貯金ですね。親が認知症になった場合、銀行口座が凍結されてしまいます。銀行により対応が様々なようですが、基本的には現金を引き出すことができないと考えておいたほうがいいでしょう。もちろん、子供が代理人として引き出す事もできません。
そして不動産。大きな財産は不動産という家も多いと思います。親が認知症になった場合は、不動産の売却や賃貸にして収益を得る事はできません。
意思能力(正しい判断ができる状態)が無くなると例え実の子供でも親の資産を自由に扱うことができなくなります。万が一に備え対策をしておくことが必要になります。信託銀行などに費用を払えば様々なサービスを受けることができますが、できるだけ費用をかけずにできる対策を幾つか考えてみたいと思います。
認知症の親の資産を凍結させない対策3つ
タイトルの書き方を迷いましたが、子供が親の介護の為に親の資産を使えるようにしておく事が必要だと思っています。親の年金や子供のお金で十分な場合は良いですが、少しでも不安がある場合は家族で話し合って予めどのような手続きをするか決めておくのが良いと思います。先ほど書いた通り、我が家でも正月に親子3人で話をしました。すぐに結論を出すのではなく数年後に決めようね、という事で以下の3つの方法について説明をしています。
- 相続時精算課税制度を利用した贈与
- 法定後見制度
- 家族信託
いずれも少額で手続きが可能な制度です。相続時精算課税制度は生前に子供たちに贈与をするが、贈与税ではなく相続税として親が無くなった時に他の相続財産と合算し計算の上で納税します。一般的には贈与税より相続税の方が低率なるためこの制度を利用します。ただし、不動産については相続時に比べると登録免許税等の費用が余計に必要となってしまいますので注意が必要です。法定後見制度は多くの場合、家庭裁判所から専任された専門家が後見人になりますが、家族が後見人になることも可能なようです。最後の家族信託は親の財産を家族に託す契約です。信託銀行などに管理を託すわけではなく、家族に託しますので高額な報酬が発生する事はありません。
この3つ以外にも費用をかけずにできる事があると思います。まずは家族で話し合いをするのが必要だという事で例に挙げました。我が家では、「ふむふむ」という反応で、「5年後までに決めようね」という話になり、それぞれ自分でも考えてみるという事になりました。備えあれば患いなし。まずは、様々な方法を調べてみてはいかがでしょうか?